

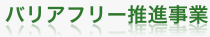
バリアフリー推進事業の成果
2022年度の事業

- 海上交通バリアフリー施設整備推進
- 海上交通バリアフリー施設整備推進
離島等における高齢者・障害者等の日常生活や社会生活に必要な移動の円滑化を推進するため、旅客船及び旅客船ターミナルのバリアフリー施設整備に対して助成した。また、「旅客フェリーにおけるバリアフリー設備の適正化に関する調査」を実施し、現行の『旅客船バリアフリーガイドライン』における課題を整理し、今後の改定方針案を示した。
-
- 共生社会実現に向けた移動円滑化基金事業
2020年パラリンピック東京大会を契機として、「心のバリアフリー」と「ユニバーサルデザインの街づくり」に取り組む「共生社会ホストタウン」における共生社会の実現に向けてパラリンピック後もレガシーとして継続することを目的に、地域における先駆的なハード・ソフト両面のバリアフリー化の取り組みに対して基金を活用した支援を行った。
空港アクセスバスについては、大分交通2台、広島電鉄1台の計3台に対し、補助金を交付した。空港施設整備については、支援に向けて関係者との協議を行った。学校施設については、津波等災害時における学校避難所のバリアフリー化に向けて、兵庫県明石市とトイレのバリアフリー等整備の補助金交付に向けた協議を行った。共生社会バリアフリーシンポジウムについては、令和5年10月に兵庫県明石市で開催し、パラアスリートによる基調講演、明石市長、福島市長による取組事例の発表のほか、地元団体等によるサイドイベントを実施した。さらに、「心のバリアフリー推進事業」として6自治体7件に対しバリアフリーマップ作成等のための助成金を交付した。
-
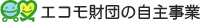
- ECOMO交通バリアフリー研究・活動助成
今後の交通バリアフリー推進に寄与することを目的として、交通バリアフリーに関わる先進的な調査研究や研究開発を行う研究者や活動を行う個人、団体等に対し7件(若手研究者部門1件、一般部門3件、研究・活動部門3件)の助成を行った。また、令和6年3月に令和4年度(令和2年度、3年度延長分含む)の助成対象事業について成果報告会を開催した。
-
- 交通バリアフリー情報提供システムの運営等
高齢者、障害者等による公共交通機関の円滑な利用のため、駅構内のバリアフリー施設、乗り換え案内のバリアフリー経路情報をインターネット等で提供するシステム(らくらくおでかけネット)の運営及び情報更新等を行った。また、他事業者間における乗換案内について、複雑な駅構内図に代わるものとして文章による乗換案内の作成と障害当事者による実地評価を行った。
-
- 交通サポートマネージャー研修の実施
公共交通従事者のバリアフリー接遇・介助水準の向上を目的としてバリアフリー研修を実施した。令和5年度は、東京で3回、関西地域で2回、神戸市交通局(地下鉄)向け研修1回、京都市交通局向け研修2回(地下鉄1回、バス1回)を実施し、合計で211名が修了した(累計修了者数2,222名)。また、個別事業者への導入編研修を2回開催した。さらに、新たな取り組みとして、旅客船事業者を対象としたバリアフリー研修プログラムの開発及びテキストの作成を行い、研修会を2回開催した。そのほか、研修の普及、改善を図るための障害当事者講師等による意見交換会(オンライン)を開催するとともに、障害者団体が実施する当事者講師養成研修を共催した。
-
- 公共交通事業者等に向けた手話教室の実施
聴覚障害者の公共交通機関による移動の円滑化を図るため、公共交通事業等に従事する者を対象とする手話教室を開催した。令和5年度は、首都圏では5名(5事業者)、大阪地区では11名(6事業者)が手話教室を修了した。
- バリアフリー普及・推進
①バリアフリー推進勉強会の開催:交通バリアフリーを推進する上でのハード・ソフトの両面の課題及び最新動向に関するバリアフリー推進勉強会を6回(東京2回、関西2回、宇都宮1回、羽田1回/日本福祉のまちづくり学会事業委員会、中央大学研究開発機構、全国空港事業者協会等との共催含)開催した。
-
②障害者団体等との連携:バリアフリー推進アドバイザーの活動として、交通サポートマネージャーの講師活動、別府港UDターミナルの周知活動、駅の乗換案内実地調査、バリアフリー推進勉強会企画会議(関西)を行った。
-
③学校並びに一般利用者等へのバリアフリーの啓発・普及活動:小学校(17件)、中学校(10件)、大学・自治体等(5件)の依頼により32ケ所でバリアフリー教育プログラムを展開した。
また、日本民営鉄道協会主催の「小学生新聞コンクール」に協力しバリアフリー賞贈呈を行った。
-
④交通バリアフリー関連文献、報告書等の収集・整理、英訳及び公開:交通バリアフリー関連文献のデータベース作成のため、文献の電子データ化を行い検索システムへのデータ追加を行った。
-
- 高齢者・障害者等の移動円滑化促進のための調査研究
①空港・鉄道駅等での障害者支援の検討:ハード・ソフトの両面から空港のユニバーサルデザイン計画を進めるため、実態把握を目的として5つの地方空港(羽田空港、新潟空港、熊本空港、宮古空港、岡山空港)の空港UD診断を実施した。鉄道駅については国土交通省関東運輸局が実施する駅の調査に同行し助言等を行った。
-
②大阪・関西万博における移動と交通に関する課題把握とソフト対策の検討:障害当事者等が参加する「大阪・関西万博に係る交通事業者のバリアフリーソフト対策検討会」において交通事業者等の接遇教育に資するため「バリアフリーサポートbook」を作成した。令和6年度は当該冊子を用いた研修会セミナーを開催する予定である。
-
③サイン等に関する調査:案内用図記号関連の委員会(JISZ8210原案作成委員会/同分科会、案内用図記号のデザイン原則及び試験方法JIS委員会/同分科会、JISZ9098原案作成委員会/分科会、ISO/TC145/SC1国内委員会)に参加し、今後のサイン関連の検討を進める上での現状把握を進めた。
-
④バリアフリー整備ガイドラインに関するニーズ・整備事例の把握及び周知:国土交通省総合政策局バリアフリー政策課が主催する移動円滑化評価会議にオブザーバ参加するとともに今後の取り組むべき課題等についての意見交換を行った。また、国土交通省国際政策課の依頼によりASEAN交通施設バリアフリー外部評価に参加しジャカルタとバンコクの旅客施設評価及び現状把握を行った。
-
⑤認知症等見えにくい障害に対する移動円滑化推進と評価:認知症者の交通機関利用を支援する「おでかけサポートカード」等の普及を図った。また、失語症のための「サポートカード」を検討、作成した(令和6年度公開予定)。また、発達障害、知的障害など見えにくい障害への対応については「ひまわり支援マーク」のトライアルを継続した(新千歳、成田、羽田、福岡、那覇の5空港)。トライアルは令和5年度で終了し、令和6年度から運用主体を(一社)全国空港事業者協会に移管することとなった。また、「センサリールーム」「Quiet room」「Hidden Disabilities Sunflower(ひまわり支援マーク)」等見えにくい障害に対する様々な対応を実施している英国にて実施団体へのヒアリング調査を行うと共に、事例収集を行った。さらに、飛行機を利用した発達障害者とその家族を対象とした持続可能なツアー実施を検証するため、日本航空株式会社・㈱ジェイエア、中央大学研究開発機構と共に「アクセシブルツアーin山形」を実施した。
-
⑥国内外の各学会・大学等との連携及び先進事例の把握:バリアフリーに関連する学会への参加、共催セミナー等を実施した。また、台湾デザイン研究院と交通機関旅客施設のサインシステムやユニバーサルデザイン全般にかかる相互協力を取り決めた覚書を締結した。
-
-
-
-